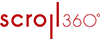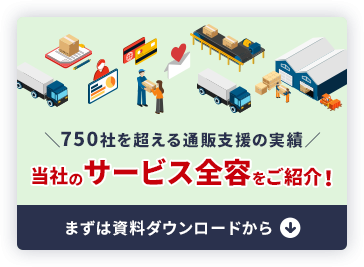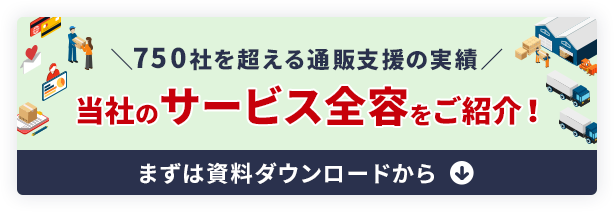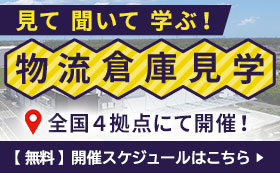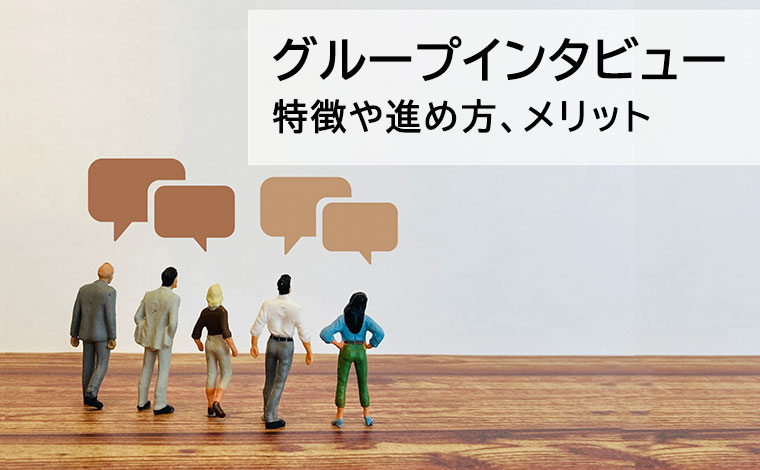
グループインタビューとは複数人の顧客に対して座談会形式で進めるインタビューを意味します。短時間で顧客の声を直接聞けるため、顧客理解を深めるためによく活用される手法です。
本記事では、グループインタビューの特徴や進め方、メリット・デメリットを解説
します。
目次
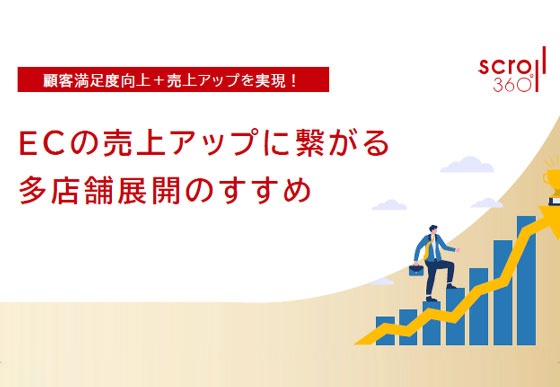
ECの売上アップに繋がる「多店舗展開」、
メリットや成功の秘訣を具体例と共に解説!
1グループインタビューとは

グループインタビューとは、複数人の顧客に対して座談会形式で進めるインタビューで、顧客理解におけるマーケティング手法の1つとして活用されています。
参加者同士の議論を活性化させることで、より多くの意見を収集できるメリットがあります。そのため、アンケート調査や1対1のインタビューでは表面化しなかった顧客の深層心理に迫ることが可能です。
グループインタビューの目的
理由1:最適な顧客体験(CX:カスタマー・エクスペリエンス)が調査できる
まず商品やサービスを売るためには競合との差別化が必須ですが、機能や性能といった部分では大きな差がつきません。そのため、購入過程や購入後のフォローといった顧客体験(CX)において差別化を図ることが重視されています。このCXをよりよいものにするためには「顧客理解」が欠かせません。
理由2:サービスや商品の改善に繋げることができる
グループインタビューを通して、顧客の解約・離脱理由を究明し、「顧客の困りごと」や「欲しい情報」を明らかにすることで、サービスや商品の改善に繋げることができます。
理由3:効率的かつ効果的なマーケティングができる
顧客理解を深めることで、以下のマーケティング施策が可能になります。
【顧客理解が欠かせないマーケティング施策例】
- 適切なCRM設計の構築
- ズレのないペルソナ、カスタマージャーニーマップの作成
- ニーズに合致した無駄のないマーケティング戦略の展開
顧客理解ができていない状態でマーケティングを進めても、思った通りに商品やサービスが売れず、無駄な施策に対するコストが増えていきます。効率的かつ効果的にマーケティングを行うためにも、グループインタビューによる顧客理解が重要になります。
2グループインタビューでわかる情報
グループインタビューからは、顧客理解を深めるために重要な以下3つの情報がわかります。

- 顧客のニーズ
- 顧客の属性や行動
- 商品・サービスの評価
顧客のニーズ
以下のような項目をグループインタビューで明らかにすることで、顧客のニーズをより深掘りすることが可能です。
| 顧客の種別 | 購買心理 |
|---|---|
| 利用中の購入者 | ・商品やサービスを知った経緯、媒体 ・購入の動機 ・配送状態 ・使用した感想 |
| 退会した購入者 | ・商品やサービスを知った経緯、媒体 ・購入の動機 ・配送状態 ・使用した感想 ・退会理由 |
顧客の属性や行動
たとえば「乳幼児向け商品」の場合、使用者は乳幼児ですが、購入者は保護者とわかれています。この場合どちらか片方だけでなく、両者の属性や行動を明らかにすることで適切なペルソナやカスタマージャーニーの作成が可能です。
商品・サービスの評価
グループインタビューでは、利用中の顧客だけでなく利用を中止した顧客(退会者)の声を拾うことで、商品やサービスの改善に繋げます。
さらに商品やサービスそのものだけでなく、同梱物であるパンフレットや販促品についての感想も聞くことで、アプローチ方法の改善も可能です。
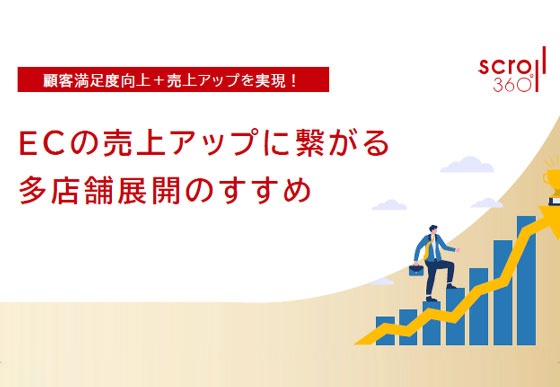
ECの売上アップに繋がる「多店舗展開」、
メリットや成功の秘訣を具体例と共に解説!
3グループインタビューのメリット
グループインタビューのメリットは、以下の4つです。

- 顧客から直接情報を得ることができる
- 議論から顧客の深層心理が見えやすい
- 複数の意見を一度に集められる
- 短時間で実施できる
顧客から直接情報を得ることができる
アンケート調査や購買行動データの数字だけを追っていくと、ニーズを捉えきれずズレが生じ、机上の空論になりがちです。グループインタビューでは、顧客の声や表情といった付加情報も得ることができるメリットがあります。
モデレーターの手腕によっては、アンケート調査では難しい顧客の本音を引き出せることもあるため、より真に迫った情報を集めることが可能です。
議論から顧客の深層心理が見えやすい
グループで議論することで、1対1のインタビューでは話すことのなかったことでも、他の参加者の意見から派生して意見が生まれることもあります。
顧客の深層心理を引き出しやすいため、商品やサービス改善の大きな材料になるでしょう。
複数の意見を一度に集められる
グループインタビューでは、複数の顧客に参加してもらうため、短時間でバラエティに富んだ多くの意見を集めることができます。さらに複数のグループを同時に進行することで、1度の実施でより多くの声を集めることが可能です。スムーズにグループインタビューを進行するためには、専用施設の利用がおすすめです。
短時間で実施できる
インタビュー時間は、1グループあたり2時間程度が一般的です。1グループを4名として3グループで別々に実施したとしても、合計6時間で終了します。
このようにグループインタビューは、短時間で複数の意見を集めることができるため、人手不足の事業所やマーケティンググループにおいて効果を感じやすいでしょう。
4グループインタビューのデメリット
グループインタビューのデメリットは、以下の4つです。

- モデレーター(司会者)の技量が問われる
- 意見に偏りが生まれる場合がある
- 日程調整に手間がかかる
- コストがかかる
モデレーター(司会者)の技量が問われる
グループインタビューは、モデレーターつまり司会者の技量によって、引き出せる情報量や質が変わります。そのため実施の際は、技量の高いモデレーターに依頼することが大切です。
質の高いモデレーターを起用するためには、グループインタビューの経験や実績が豊富な事業者が提供するアウトソーシングサービスの利用も検討しましょう。
意見に偏りが生まれる場合がある
本音を話しにくい空気ができてしまうと、隣の人に意見を合わせてしまい、意見に偏りが生まれる場合があります。
他にも、主旨とはズレた話題で盛り上がってしまうと、必要な情報を集めることができません。
グループインタビューで参加者がざっくばらんに本音を語るためには、質問内容の優先順位や時間配分などの綿密な進行準備や、当日のスケジュール管理、質の高いモデレーターが必要です。
日程調整に手間がかかる
グループインタビューは、複数人の参加者を集める必要があるため、日程調整に手間がかかります。特にインタビューの対象者が決まっている場合は、余裕をもったスケジューリングが必要です。
参加者を募集する場合は、グループインタビュー実施日の2ヵ月前に募集を行うことが一般的です。
コストがかかる
グループインタビューの実施には、下記のようなコストが発生します。
- 会場利用料
- 参加者への報酬、交通費
- アウトソーシング利用料
オンラインで実施する場合は、会場利用料や交通費を削減できますが、参加者がオンラインに慣れていないと、上手く接続ができなかったり、画面越しでは消極的になり、議論が盛り上がらない可能性があります。グループインタビューは可能な限りオフラインで行い、必要なコストは前もって予算立てしておきましょう。
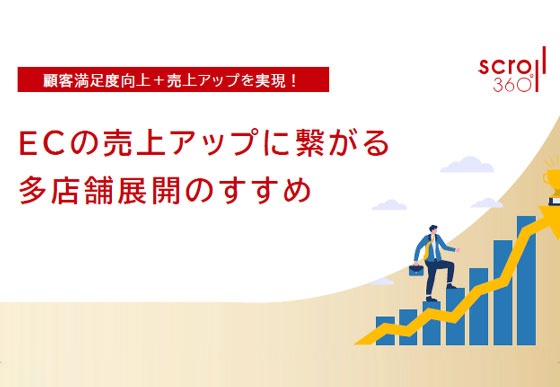
ECの売上アップに繋がる「多店舗展開」、
メリットや成功の秘訣を具体例と共に解説!
5グループインタビューを行うべき場面

実際に商品やサービスを使う「顧客の生の声」を交えることで、顧客の真のニーズを導き出し、自社の社員だけでは考えもしなかった改善方法が見つかる場合があります。
グループインタビューを行うべき場面は、以下の通りです。
- 顧客ニーズに対する仮説・ペルソナの洗い出しや検証
- マーケティング戦略立案・効果立証
- 既存商品やサービスの改善点の究明
- 新商品や新サービスに対する反応の確認
- 商品パッケージや梱包状態への意見の収集
- チラシやパンフレットなどの同梱物に対する意見の収集
あらゆる意見を集めることで、顧客の真のニーズを導き出すことも可能です。
6グループインタビューの進め方
グループインタビューは、以下6つの手順に従って進行します。
ここでは、健康サプリを扱っているEC通販事業者の事例をもとに、手順を解説します。

- 目的の明確化
- 企画立案と参加者の募集
- モデレーターの依頼
- ヒアリング項目の整理
- インタビューの実施
- 分析とCRM設計
1. 目的の明確化
子ども向けの健康サプリを扱っているEC通販事業者がグループインタビューを行う場合、目的は3つ考えられます。
| グループインタビューの目的 | 理由 |
|---|---|
| 顧客のプロフィールを明らかにする | 適切なペルソナとカスタマージャーニーを設定するため |
| 顧客の購買心理を明らかにする | サイトの表現やパッケージデザインなど、さまざまなマーケティング施策を見直すため |
| 顧客の同梱物への評価をもらう | あったほうがよいもの、なくてよいものを明らかにして取捨選択するため |
グループインタビューの具体的な実施方法と分析方法を定めるためにも、目的の明確化は必要です。目的は1つに絞る必要はなく、上記のように複数設定しても構いません。
2. 企画立案と参加者の募集
企画立案の中では、以下の内容を決め、参加者をタイプごとにグルーピングしてからスケジュールに沿って募集しましょう。
【企画立案で決める内容】
- 実施目的
- グループインタビューの実施時間(2時間が望ましい)
- 1グループあたりの人数(商品やサービス、実施目的によって異なる)
- 実施グループ数
- 実施会場
- 分析方法
- モデレーターを依頼する会社(アウトソーシングサービスに含まれる場合あり)
- 利用するアウトソーシングサービス(利用する場合)
【参加者のグルーピング例】
- ロイヤルカスタマー(○カ月以上の継続優良顧客)
- 新規定期購入者(新規購入後○ヵ月以内)
- 退会離脱者(○ヵ月以内に退会)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 1月上旬 | メールにて募集開始 |
| 1月中旬 | 参加応募の申込締め切り ※募集開始から2週間で締め切る |
| 1月下旬 | 当落メールの送付 |
| 2月下旬 | グループインタビュー実施 |
| 3月上旬 | レポート・報告書提出 |
| 3月中旬 | CRM設計提案・改善案 |
3. モデレーターの依頼
前述のとおりグループインタビューはモデレーターの技量によって得られる情報の量と質が左右されるため、予算をつけてプロへ依頼することが望ましいです。
グループインタビューのアウトソーシングサービスを利用する場合は、サービスにモデレーターの依頼が含まれることが大半です。事前にモデレーターの有無を確認してから、委託先を決めるようにしましょう。
なお、依頼する会社は企画立案のタイミングで決めておくとスムーズです。
4. ヒアリング項目の整理
目的とグループ属性に合わせて、グループごとにヒアリング項目を作成します。今回の例では、次の項目に合わせてヒアリング項目を作成するようにしましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | ・顧客のプロフィールを明らかにする ・顧客の購買心理を明らかにする ・顧客の同梱物への評価をもらう |
| グループ属性 | ・ロイヤルカスタマー(1年以上継続購入) ・新規定期購入者(新規購入後1ヵ月以内) ・退会離脱者(1ヵ月以内に退会 |
グループインタビューに慣れていない場合は、ヒアリング項目の作成を含むアウトソーシングサービスの利用を検討しましょう。
5. インタビューの実施
用意したヒアリング項目をもとに、モデレーターが各グループでインタビューを進めていきます。今回の例では、以下のように実施時間と参加人数を定めました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時間 | 1グループあたり2時間 |
| 1グループあたりの人数 | 4名 |
| グループ数 | 3グループ |
| 参加者合計人数 | 15名 |
インタビューの実施は、専用施設での開催が適切です。グループインタビューを進める様子をマジックミラー越しに様子を観察できるため、参加者の表情や声といった付加情報の収集に専念可能です。うまくアウトソーシングサービスを活用して、グループインタビューの質を高めましょう。
6. 分析とCRM設計
グループインタビューが終わったら、すぐに分析に移ります。今回の例では、退会離脱者に対するインタビューで、次のことがわかりました。
- 平日の朝は忙しいためサプリを飲ませ忘れることが多い。
そのため、朝夕2回飲むべき錠剤が1ヵ月後には30錠ほど余ってしまい、休会および退会につながった - 幼児向けサプリとのことで、子どもの小学校入学をきっかけに退会する
退会理由が明らかになったところで、CRM設計に入ります。
| 改善内容 | 施策 |
|---|---|
| 飲み忘れても夕飯前後に2回飲んでよいというメッセージを送る | 先輩ママからのアドバイスを載せたチラシを初回から3回分発送分まで同梱する |
| 小学生向けサプリを開発 | 小学校入学とともに切り替えを促す |
このように退会離脱者に対してだけでも、非常に具体性をもった改善策が浮かび上がることがわかります。グループインタビューで得た情報をもとにすれば、より多くの改善策が見えてくるはずです。
CRM設計が終わると、次はペルソナとカスタマージャーニーの設定を行い、ユーザー像の統一と共有によって、意味のある施策を打てるように改善します。
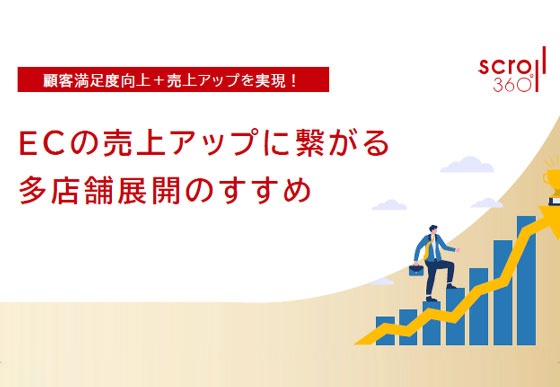
ECの売上アップに繋がる「多店舗展開」、
メリットや成功の秘訣を具体例と共に解説!
7グループインタビューを成功に導くコツ
グループインタビューを成功に導くためには、以下の3点を押さえることが大切です。

- 募集時にセグメント設定をする
- 事前準備を念入りに行う
- テーマ・グループ属性に合わせてヒアリング項目を作成する
1. 募集時にセグメント設定をする
前述のとおり、タイプごとにグルーピング(ロイヤルカスタマー、新規定期購入者、退会離脱者)することで、議論が深まりやすくなりますが、まず参加者が集まらなければ何も始まりません。参加者を効率よく集めるには、以下のように募集時のセグメント基準を決めることが重要です。
【セグメント基準例】
- 開催場所に近い住所(東京都開催の場合は、一都三県)
- 同性(女性のみ、男性のみ)
- 年代(ターゲット年齢:○~○歳の間のみ)
先にセグメント基準を決めておくと、効率よく募集できるほか、実際のインタビュー時も意見が活性化されやすい傾向にあります。メール募集の場合は、普段からメルマガ配信を積極的に行っていると、募集をかけた際にメールアウト数の10%前後の応募が見込めます。
しかし、そうでない場合は1%未満に留まるため、芳しくない応募状況の際は、必要に応じてセグメントを広げメールアウト総数を増やすようにしましょう。
またメルマガを配信していない場合や・普段メールでコミュニケーションをとらない場合は、封書で募集する方法も合わせて検討しましょう。
2. 事前準備を念入りに行う
募集は開催日の2ヵ月前に行い、以下の対応のための十分な準備時間を確保します。
【事前準備】
- 事前アンケートの実施
- 応募者からの質問回答
- 会場予約・設定
- キャンセルがあった場合の対応
- 当日質問の内容精査(深掘りしたい内容など)
この準備で当日の進行や意見の質が大きく異なるので、ひとつひとつ丁寧に対応しましょう。
3. テーマ・グループ属性に合わせてヒアリング項目を作成する
限られた時間内で質の高い意見を集めるために、「ヒアリング項目の作成」はグループインタビューの成功を左右すると言っても過言ではありません。
グループ属性によってもヒアリングすべき内容は変わるため、必ずグループごとに検討するとともに、事前アンケ―トの結果をもとに「アンケートのみで完結」「インタビューで深掘りしたい質問」など優先順位をつけて内容精査しましょう。
例えば目的を次の3つに定めた場合、ヒアリング項目は表のようになります。
【目的】
- 顧客のプロフィールを明らかにする
- 顧客の購買心理を明らかにする
- 顧客の同梱物への評価をもらう
| ヒアリング項目 | 内容 |
|---|---|
| プロフィール確認 | ・住所、氏名、年齢、属性など(※事前アンケートで把握してもよい) |
| 商品購買心理(購入前) | ・商品を知った経緯 ・購入の決め手 |
| 商品購買心理(購入後) | ・購入前の不安 ・使用後の感想 |
| 同梱物の評価 | ・同梱物の感想 ・同梱物の必要性 |
| 今後の商品開発について | ・欲しい商品 ・購入可能な値段 |
| 販売方法についての意見 | ・定期購入方法に関する意見 |
| その他希望等 | ・割引サービスが欲しい、など |
新規定期購入者の質問項目を基準に考えると、ロイヤルカスタマーには「商品の継続購入理由」を聞く必要があるとわかるでしょう。このように、目的とテーマ、グループに合わせたヒアリング項目を作成することを心がけてください。
8まとめ:グループインタビューを実施し顧客理解を深めよう
グループインタビューでは、アンケート調査や1対1のインタビューにはない顧客の本音を引き出し、顧客理解の深度を高めるよさがあります。
成功させるためには、経験が豊富なモデレーターの起用や、適切なヒアリング項目の作成が必要です。グループインタビューの実施経験が浅い場合は、アウトソーシングサービスを活用して業務を委託し、技術を学ぶとよいでしょう。
当社では、長年の経験で培った経験・ノウハウをもとにグループインタビューの目的設定から当日の進行まで、本記事で紹介した内容を一括して支援しています。グループインタビューをご検討の際は、お気軽にご相談ください。
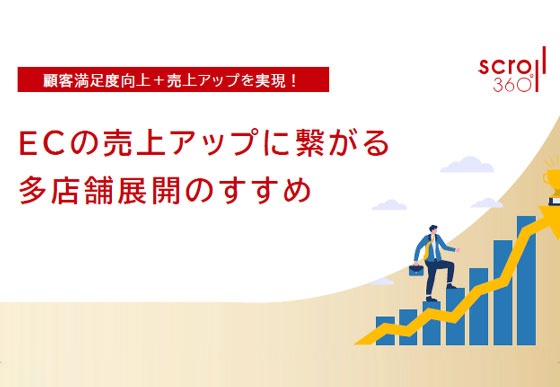
ECの売上アップに繋がる「多店舗展開」、
メリットや成功の秘訣を具体例と共に解説!
サービスはこちら